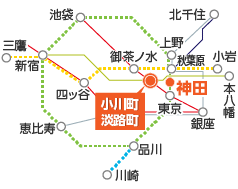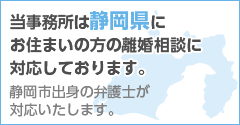経営者・資産家の離婚
離婚を考えている経営者・資産家の方からよくあるご相談
- 離婚すると会社の経営権はどうなるのか
- 共同経営者である配偶者とどうしたらうまく離婚できるか
- 自分が持っている株式を財産分与せよ迫られている
- 個人資産と会社資産は別扱いになるのか
- 配偶者(又は親族)が所有する不動産を会社が賃借している
- 離婚後も安定して自分が会社を経営できるようにしたい
- 別居中の配偶者から高額な婚姻費用を求められている(又は求めたい)
- 配偶者には分与したくないが子に会社や資産を継がせたい
経営者や資産家の場合、配偶者も一緒に経営に携わっている場合や、会社株式を持っている場合は特に注意が必要です。
やり方を間違えると会社の経営権自体を失い、取り返しのつかない状態に陥りかねません。離婚を考える場合には、よくよく慎重に準備をすることを強くお勧めします。
目次
経営者・資産家の離婚特有の問題
1.配偶者が事業に関与している場合
配偶者が事業に関与している場合、離婚に向けての十分な準備が必要です。
例えば、配偶者が現場を取り仕切っていたり、従業員に影響を有する立場である場合、夫婦仲が悪くなると他の従業員に吹聴して職場環境を悪化させ、または他の従業員を自身の味方につけて労務問題を発生させるなどのリスクがあります。配偶者がその事業に欠かせない技術者であったりすると、離婚により事業の遂行に重大な影響が生じます。配偶者が役員に入っている場合は、役員会の運営に支障が生じ、役員会の議決ができないなどのリスクが発生します。
その他、配偶者や配偶者の親族の個人資産を会社が賃借(又は無償で借りている)し、または金融機関からの借入金の担保に入れている場合は、離婚によりその関係性を終了せざるを得なくなりうることも大きなリスクです。
2.配偶者が会社株式を有する場合
配偶者が会社の株式を保有している場合、さらに問題は複雑となります。
例えば、自身が50%、配偶者が50%の株式を有していた場合、決算決議すらできなくなりデッドロックに陥ります。すなわち、株主総会の普通決議は、株主の議決権の「過半数」(会社法309条1項)が必要であるところ、ご自身が有する50%の株式では過半数が取れません。したがって、配偶者の賛成がない限り、会社の通常経営自体もできないことになります。
また、株式の3分の1以上を配偶者(又はその親族)が保有している場合は、ご自身だけでは3分の2以上の特別決議は取れませんので、定款変更などはできません。そこまで行かなくとも、一定の株式を有していれば少数株主権を行使されることで会社経営に事実上様々な支障が生ずることになります。
したがって、会社の株式は配偶者から全て譲り受けたいところです。もしそれができない場合には、会社経営に重大な支障がでないようなスキームを検討することが必要です。
3.財産分与対象となる財産について
経営者・資産家の離婚の場合、財産分与額が高額になるため、多くの場合、そもそも財産分与対象財産がどの範囲か、またその評価額はどうするかの問題が生じます。
①財産分与の対象となる財産の範囲
財産分与対象となる財産の範囲は、原則的には「結婚してから離婚(又は別居)するまでに夫婦共同で築いた財産」です。したがって、独身時代に形成した財産、相続により取得した財産、別居後に形成した財産は原則的には対象外となります。
しかし、独身時代に形成した財産であっても、婚姻後に形成した財産と混在した場合(例えば同一口座での入出金がある場合)は、婚姻前に形成した財産でも基準日(別居日又は離婚日)の残高を基準として財産分与対象となってしまうため注意が必要です。これを避けるためには、結婚当初から財産を分離するか、既に混在してしまっている場合には、自己のみに帰属すべき「特有財産」であることの立証が必要です。当該立証は、特有財産であることを主張する側に立証責任があるため、取得原因、使途、過去にさかのぼって当該金銭がどのように移動しているかの紐づけ作業などが必要になりますので、特有財産立証に慣れている弁護士に依頼されることをお勧めします(当事務所は上記に対応しております)。
②財産分与の対象となる財産の把握方法
財産分与対象財産は、まずは任意で資料を出し合い把握することが原則です。したがって、相手方が財産を隠す場合に備えて、離婚交渉前からどのような財産を保有しているか、できる限り把握しておいた方がよいでしょう(例えば、どのような金融機関、保険会社から郵便物が来ていたかを把握しておくだけでも後々楽になります9.
しかし、相手方の財産が全く分からない場合は、法的手続きを利用して財産を開示させることになります。例えば、
- 弁護士会照会による調査
- 裁判所の調査嘱託・文書提出命令を利用した調査
などがあります。
その他、通帳履歴や給与明細等から財産が判明することも多いので、まずはお手元の資料を精査していただくことでもある程度明らかになります。
③財産分与対象財産の評価額について争いがある場合
評価額について争いがある場合、まずは交渉によりご自身に有利な金額を引き出します。交渉でも決着しない場合、最終的には、裁判所による鑑定を利用します。但し、鑑定費用は不動産単体で50万円前後、株式評価になると100万円前後と高額になりますので、可能であれば鑑定を避けた方が良い場合もあります。ご相談者様の状況により異なりますので、お悩みの方はご相談ください。
経営者・資産家が離婚を考える際に考えるべきポイント
経営者や資産家が離婚を考える場合、離婚後も会社を円滑に経営できるか、先祖代々引き継いだ大事な資産を守れるかが重要です。
まずは以下のポイントをチェックしてみてください。いずれか1つでも満たしている場合は要注意です。
- 配偶者又は配偶者の親族が会社の株主か、その割合が合計で3分の1以上か
- 配偶者又は配偶者の親族が会社の役員に入っているか
- 事務所や工場に使用している不動産のうち、配偶者又は配偶者の親族が所有しているものがあるか
- 担保に入っている不動産があるか
- 配偶者の存在が当該事業に必要か(配偶者がいなくても事業は回るか。難しい場合は支店設置、分業なども検討できるか)
- 許認可事業か(当該資格者が配偶者のみか)
- 後継者候補(子ども)がいるか
※後継者候補(子ども)がいる場合で、配偶者に株式等の財産分与を避けたい場合には、離婚の問題だけではなく、株式譲渡(事業承継)、遺言、民事信託などを検討すべき場合があります。
当事務所のメリット
経営者・資産家の離婚問題は、夫婦間の離婚問題だけにとどまらず、会社全体や、一族の問題にかかわります。安定した経営権の確保や労務問題、将来的には事業承継(株式の譲渡、遺言、民事信託)などの問題が発生します。
当事務所では、このような問題にも広く対応が可能であり、登記・税務・社会保険関係も提携する司法書士・税理士・社会労務士その他専門職とともにワンストップサービスを提供しております。また、顧問先は中小企業様がメインであり、顧問先の案件は全て代表弁護士が担当しますので安心です。
また、経営者や資産家の配偶者を相手とした交渉ももちろん可能です。経営者や資産家の離婚に伴うポイントがわかりますので、お客様に有利な交渉を行うことが可能です。
初回相談は45分5000円+税で行っておりますので、もしご不安な方は一度当事務所にお気軽にご相談ください。